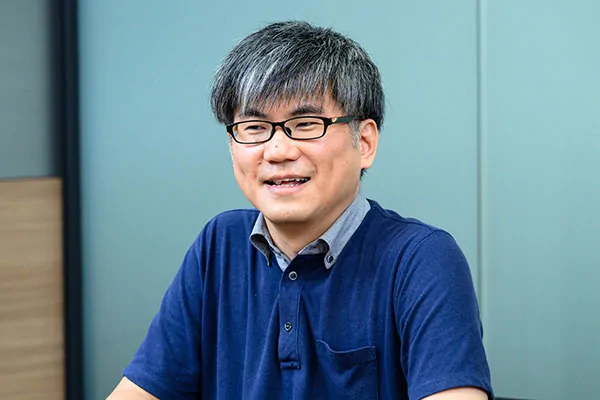トランスフォーメーション活動と経営課題を紐づける2022年
ニューノーマルはすでにノーマルとなり、街の鼓動は再び力強く脈打ちはじめている──。
そんななか日本の業界関係者たちは、2022年にどんな課題を感じ、どんな可能性を見出しているのか? この年末年始企画「IN/OUT 2022」では、 DIGIDAY[日本版]とゆかりの深いブランド・パブリッシャーの株式会社SUBARUにて、デジタルイノベーション推進部 主事を務める小川秀樹氏に伺った。
──2021年に得たもっとも大きな「成果」はなんですか?
DXが本質的に議論されるようになり、全社の活動へと拡大していったことです。デジタルやデータが媒介となって部門の壁を壊し、特にモノ作り領域の顧客志向へと繋がってきました。また、CRMは深みを増し、ロイヤリティ施策だけではなく拡大するためのマーケット開拓へ、既存ビジネスも新規ビジネスも改革や改善に大きく進んだこの1年でした。
──2021年に見えてきたもっとも大きな「課題」はなんですか?
半導体不足などをはじめとして、モノが作れなくなる危機に対峙し、製造業において販売だけでのビジネスモデルの危うさを強く感じました。販売後のビジネスの割合を高めていくことが生き残りにおいても急務であると強く意識しました。そしてそのスピードに追い付けていない課題が明らかになりました。
──2022年にもっとも注力したい「取り組み」はなんですか?
トランスフォーメーションの活動と経営課題を紐づけ、デジタルやマーケティングが営業、商品側だけではなくモノ作りを含めた全社活動の当然のものとして定着するよう仕組化すること。そして変わり続けることを継続的に行えるよう、実例のアウトプットを用いながら人材育成・風土改革をリードしていきたいと思っています。
───下記は以前、対談企画のもの。この機会に是非ご一読ください。───
SUBARU が切り拓く、プログラマティック・ブランディング :「すべてのアクションを計測できる」
自動車の国内需要が低下しつつあるなか、自動車メーカー各社は厳しい競争環境に晒されている。このような状況下で重要になるのは、誰に何をどのように自社(ブランド)の広告を届けるべきか、というシンプルな視点だ。
SUBARUの国内営業本部 営業支援部 ITグループ アシスタントマネージャーの安室敦史氏は一例としてその相手を、「SUBARUのブランドや商品を認知はしているが購買に至っていないお客様だ」とし、こう続ける。「そうしたお客様のプリファレンスを高め、さらにはアクションを促すようなブランディングと販売促進が必要になる」。
プログラマティック広告のブランディング利用における成功事例はあまり多くない。しかし、SUBARUは豊富なデータに基づく精緻なオーディエンスのターゲティング、ブランディングを実現しているという。
「選ぶ力」を与えるプログラマティック
2月26日にDIGIDAY[日本版]が開催した会員イベントDIGIDAY Salonでは、前述の安室氏に加え、スバルITクリエーションズのデータサイエンティスト・データデザイナーである小川秀樹氏、ザ・トレード・デスク・ジャパン(The Trade Desk Japan、略称:TTD)の新谷哲也氏らが登壇。SUBARUのプログラマティック・ブランディングの最新事情に迫った。
プログラマティック広告といえばリターゲティングというイメージが強いが、ブランディングも含めたアッパーファネルの配信方法と捉える広告主が着々と増えていると新谷氏は指摘する。「プログラマティック広告は広告主がファーストパーティデータを使い、どのインプレッションを買うかを選ぶ力を持つものだ。必要なユーザーのインプレッションを買うことができ、精緻なブランディングを実現できる」。
幸いなことに、SUBARUには豊富なファーストパーティデータが存在した。たとえば、全国44社のディーラーが有する顧客データだ。本来各ディーラーは競合同士であり、自社データをメーカーに提供することはない。「国内メーカーでこれを実現しているのはSUBARUだけだ」と安室氏は語る。さらに、2017年から展開しているオーナー向けアプリ「マイスバル」によって、約40万人分の顧客データも蓄積。しかし、これらの膨大な顧客データはバラバラに散在している状態だった。
小川氏も、「せっかく高度な取り組みとしてファーストパーティデータが蓄積されているのに、結局はアクセス解析やサードパーティのデータを利用していたため精緻なターゲティングができず、そもそも結果がどうなったのかすらわからないという根本的な問題があった」と当時を振り返る。「自社データを活用してセグメントを作ることに取り組み、オフラインも含めた可視化を実現したいと考えた」。
そこで、CDPであるトレジャーデータを導入し、各データを顧客軸で統合。購買に至る行動ログの理解やWeb広告の最適化、オウンドメディアを訪れたユーザーへの情報の出し分け、ディーラーの支援にも取り組むことが可能になった。さらに、「いままで分断されていたWeb広告の効果やテレビの接触ログ、自社サイト・セカンドパーティメディアのログ、イベント参加者データなどもすべてつながった」と、小川氏は続ける。「すべてのアクションが購買につながったかどうかを計測できるようになったことは、非常に大きい」。

「お客様のプリファレンスを高めることを目指した」と語る安室敦史氏
ブランディング全体を捉えられるか
SUBARUのプログラマティックを活用した、データドリブンなブランディングが成功したのはなぜなのか。同社が、課題とそれに対する具体的な解決策や透明性の提供、プランニングといった要素を包括し、全体を捉え、TTDをプラットフォームとして活用したからだと、新谷氏は指摘する。
「多くのブランドはプログラマティックと聞くと、アドプロダクトなど個々の話になりがちだ。私自身、エージェンシーやブランドの担当者と会話をしていても各論に陥ってしまい、話が噛み合わないと感じることが少なくない。エージェンシーやメディアの業務が細分化され、各オペレーションの運用については優秀な人材は揃っているが、一方でそれを統合できる・するべき人材が不足していると考えている」。
安室氏も「ブランディング全体ではなく、個々のデータやテクノロジーの部分だけでしかパートナーと会話ができないのは残念だ」と同意する。「ブランドにとっては誰が顧客で、何を提供すべきなのかが大前提にあり、その先にプランニングや運用、データがある。ブランドと一緒に全体を理解してくれるパートナーと仕事をしたい」。
そのため、安室氏らはデータをパートナーと共有することを前提とし、それができないDMPは導入しないという方針のもと、CDPの導入に至った。「各車種でエージェンシーが異なるため、全員がお客様に何をどのように提供するのか考えるためには、全員でデータを共有する環境が必要だった。結果的に、それが透明性を持ったデータドリブンの実現にもつながった」。

「各論ではなく全体を捉えることがプログラマティック・ブランディングには必要」と語る新谷氏
プログラマティックを超えた領域へ
SUBARUの取り組みは、すでにプログラマティックという領域を超えつつある。そのひとつが、顧客一人ひとりが購入に至るまでのカスタマージャーニー(行動ログ)を詳細に記したデータだ。同社の基幹システムから導き出されたデータから個人情報を削除したうえで、Web上でのページ閲覧時間や閲覧時系列までまとめられている。
「こうしたデータから機械学習で購入に至るお客様の動きを分析し、近しい動きをしているお客様は見込み度が高いと判断している」と、安室氏は続ける。「社内でもオウンドメディアの担当者がサイトの導線を考えるための参考にしたり、広告配信において誰にいつどのような広告を見せる必要があるのか、といった検証にも用いる」。自分の予想とはまったく違うアクションを起こしている、といった情報がログベースで把握でき、それを踏まえた次のアクションも策定しやすくなったという。
「結果的に、仕事のやり方にも変化が起きた」と、小川氏は語る。「従来の、エージェンシーから結果だけ見せてもらい集計をするという姿勢ではなく、より能動的に自分たちがデータと向き合わなければいけない。変化は忌避されるもので、受け入れてもらうのは手間もかかるが、私達は今、変わらなければ未来はない。現場の担当者には『仕事の成果が数字で見えることで仕事が楽しくなった』と言ってもらえている」。

「従来の仕事のあり方を変える必要もあった」と話す小川氏
プログラマティック・ブランディング
さまざまな課題に直面しながらもSUBARUは、2019年4月に前年越えの販売台数を達成している。だが、安室氏は、広告配信やデータだけでビジネスインパクトを出せるとは考えていないと話す。「お客様の支持をいただいたおかげで、少しでも貢献ができたのではと実感している。だが、デジタルだけでこの成果につながったわけではない。あくまでも目的はお客様のプリファレンスを高め、SUBARUっていいね!と感じていただけること。全社員がそのための地道な取り組みを続けていく」。
SUBARUならではのプログラマティック・ブランディングを突き詰めていくためには、まだ社内に眠る膨大なデータの活用が求められる。そのためには、社内やパートナーへの一層の啓蒙も必要になるだろう。「データ活用や透明性、加工されていないアクセスログをいかに利用するかといった流れは、今後当たり前になるし、止めることはできない」と、小川氏も続ける。「そうした時代を迎えたとき、我々はどのように仕事をすべきなのか、どうあるべきなのかを考えなければいけないフェーズだと考えている。メディアとの関係もどうあるべきなのか、次世代のパートナーシップといった視点が求められるようになるはずだ」。
安室、小川両氏の動きに、新谷氏は期待感を寄せる。「新しいデジタル広告のあり方を模索し、変えようとする動きが、『クリック単価や顧客獲得単価で評価される広告』からの脱却につながるのではないかと真剣に期待している。TTDも変化を恐れず取り組もうとする業界の人たちとともに、次のスタンダードを作っていきたいと考えている」。
Written by 分島翔平