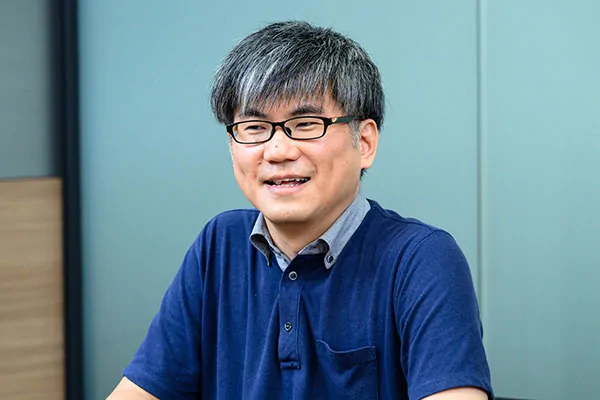SUBARUとマツダ 台数追わず「存在感」高める戦いの行方−2017
自動車産業では今、トップランナーが年間生産台数1000万台レベルでしのぎを削るほどに規模の追求が進んでいる。その一方で、小規模メーカーがターゲットとなる顧客を絞り込むことで、台数に頼らず独自の存在感を発揮するケースも増えるという“二極化現象”が進んでいる。
海外ではプレミアムセグメント、すなわち高級車を手がけるメーカーが少量生産を守ってきたが、メルセデス・ベンツを手がけるダイムラーやBMW、アウディなどが大量生産に移行。すっぽり空いた少量ブランドのポジションにスウェーデンのボルボ、イギリスのジャガー・ランドローバーなどが入り込み、急速に業績を伸ばした。
日本でも「台数は追わず存在感を追求する」と、少量生産を宣言しているメーカーが2つある。SUBARUとマツダである。
海外勢と異なるのは、少量生産をプレミアムセグメントではなく、大衆車でやっているということだ。利幅の小さな大衆車でそれをやって大丈夫かと訝る声は少なくなかったが、両社とも世界生産能力の限界付近でフル操業状態。今のところはうまく戦っていると言っていい。
少量生産によるブランディングを成功させるカギは、商品であるクルマに絶え間なく改良を加え、常にフレッシュな状態にしておくことだ。たまたま日を近くして、その2社の取り組みをテストドライブを通じて体験する機会があった。
SUBARUは8月7日、主力ステーションワゴン「レヴォーグ」とスポーツセダン「WRX」の改良モデルを投入する。それに先立って7月、伊豆・修善寺のサイクルスポーツセンターというクローズドコースで両モデルを走らせてみた。
まずはレヴォーグ。SUBARUはおよそ1年ごとにクルマに改良を施すことで知られており、レヴォーグも2014年6月にデビューしてから3回目の改良。その中で今回の改良はもっとも大規模なものだ。
SUBARU躍進の原動力となった先進運転支援システム「アイサイト」がバージョンアップし、準自動運転機能が充実。オプションでボンネット先端に広角カメラを装着することで、狭い路地から大通りに出るときのように運転席からは左右が死角となる場合でも鼻先が交差点に差しかかればモニターで死角の先を確認可能になるなど、安全支援機能についても充実が図られていた。ガラスの板厚アップなどの処置によって、静粛性も高められていた。
が、最も進歩したのは運動性能。サスペンションの構造を一部変更するなどの大手術によって、しなやかさを持たせたのだという。
テストドライブでは新型と旧型を乗り比べることができた。果たして路面状況の良い道を走るだけなら旧型のほうが一見シャープ。しかし、カーブでハンドルを切って車体がロールする動きの滑らかさ、路面がうねったところで車体が上下に揺すられてもタイヤの路面への食いつきが失われないこと、乗り心地の良さ等々、クルマとしてのトータルバランスについては新型が断然上だった。
SUBARUは昨年秋、「インプレッサ」というコンパクトモデルを発売した。先行研究から数えると8年以上をかけて作ったという全面新設計のボディ、サスペンションの仕上がりは素晴らしいもので、世界のどこに出しても胸を張れるくらいのものだったが、それが出たことによってレヴォーグが性能、快適性の両面で少なからず見劣りするようになっていた。
もちろん今回のレヴォーグの改良はフルモデルチェンジのように全部を刷新したというわけではないため、インプレッサと同じように軽く、走行抵抗の少ない走り味になったわけではない。が、走りに関する重要な部分にしっかり手を入れることで、その差はかなり詰まったという感があった。
続いてスポーツセダンのWRX。こちらもシャシー(クルマの走りを支えるサスペンションや駆動装置)に大幅な改良を加えてきた。
その改良の細かい説明は省くが、最も性能の高い「STI」というグレードの新旧モデルを乗り比べてみると、新型は旧型に比べて車重がひとまわり軽くなったのではないかと思うような敏捷性を発揮した。旧型も2014年に登場した当初、走りについては高い評価を受けてきたのだが、それをはるかに上回るフィールであった。
最も大きな違いが出るのはきついカーブでの回り込みで、コーナー出口に向かってアクセルを踏めるポイントが旧型よりひと息もふた息も早いのが印象的だった。
自動車メーカーはすべてのクルマを一気に刷新することはできない。フルモデルチェンジで良いクルマが出来ても、そのことで他のモデルが魅力を失うことがあっては、ブランド力を確立するのは難しい。レヴォーグやWRXについて、そうなることがないような手の入れ方をしてきたあたり、SUBARUは少量生産メーカーとして価値を持続的に上げていくツボをつかみつつあるように感じられた。
さて、少量生産主義に徹すると宣言したもうひとつのメーカー、マツダもまた、クルマの価値を上げるのに懸命である。マツダがこのところ取り組みを強化しているのは、安全性の強化だ。
安全性といえば、衝突回避システムなどの先進安全装備や各種警報、衝突安全ボディといった技術的なものが思い浮かぶが、マツダが取り組んでいるのはそれだけではない。商品本部の猿渡健一郎副本部長が語る。
「安全は安心に、安心はドライビングプレジャーに直結する。この3つは分けて考えるべきではない。運転の楽しさを阻害する安全上のリスクや不安要素は何かということをしっかり考えて、安全性というものをデザインしていきたい」
そのマツダの安全システムのなかで筆者が注目しているのは、ヘッドランプだ。マツダはハイビーム/ロービームの自動切換えだけでなく、ハイビーム時に先行車や対向車を避けて照射する機能を持つアクティブハイビームを2014年、ミドルクラスセダンの「アテンザ」に搭載した。
アクティブハイビーム自体はすでに普及が始まっているものだが、それを搭載しているクルマのほとんどは高級車。コストが高いからだ。が、マツダはそれを高価なモデルだけでなく、サブコンパクトカーのデミオまで採用車種を拡大した。
さらに今年6月にマイナーチェンジされた「CX-3」は、古典的なハロゲンヘッドランプの最安グレード以外、すべてのグレードについて、アクティブハイビーム機能つきのLEDヘッドランプを標準装備にした。
前出の猿渡氏は、高価なアクティブハイビームを標準装備化した理由について、
「これがあるのとないのとでは夜間走行時のモノの見え方がまるで違う。対向車が連続しているようなときも標識や道路案内の看板はくっきり見えるし、障害物の発見も早い。安心はドライビングプレジャーを支える最も重要な要素であるという観点からは、ついていて当たり前にしたい。今はまだ高価だが、他メーカーさんが標準化に追従してくれれば量産が進み、そのうち必ず安くなる」
と述べた。筆者は2月にアクティブハイビームが装着されたデミオで東京~鹿児島間を3400kmほどツーリングしてみたが、その効能は猿渡氏の主張そのもので、一度それを装備したクルマに乗ると、普通のヘッドランプには戻れないというくらいに夜間走行時の安心感は抜群であった。
SUBARUとマツダが今のところ少数派ならではの存在感を出せているのは、これまで述べたように、どういうクルマが素晴らしいのかというメーカーの哲学を明確化し、ぜひとも必要という要素は顧客が求めているか否かにかかわらず、それを商品にきっちり盛り込むことで、その哲学を外に向かって発信できていることによるところが大きい。
ただ、この道は茨の道でもある。クルマの技術はコモディティ(普遍)化が急速に進むのが特徴で、何かが顧客にウケるとみるや、大手を含むライバルがすぐさまフォローしてくるのが常だ。
その意味では両社とも、ブランド力づくりにあまり長い時間はかけていられない。ライバルに似たようなコンセプトでクルマを作られる前に「この思想は○○社がオリジナル」と多くの人が認識してもらえるようにならなければいけないのだ。
緒戦は上手い戦いを展開したSUBARUとマツダだが、ここから先が真価の問われるところであろう。
■取材・文/井元康一郎(自動車ジャーナリスト)